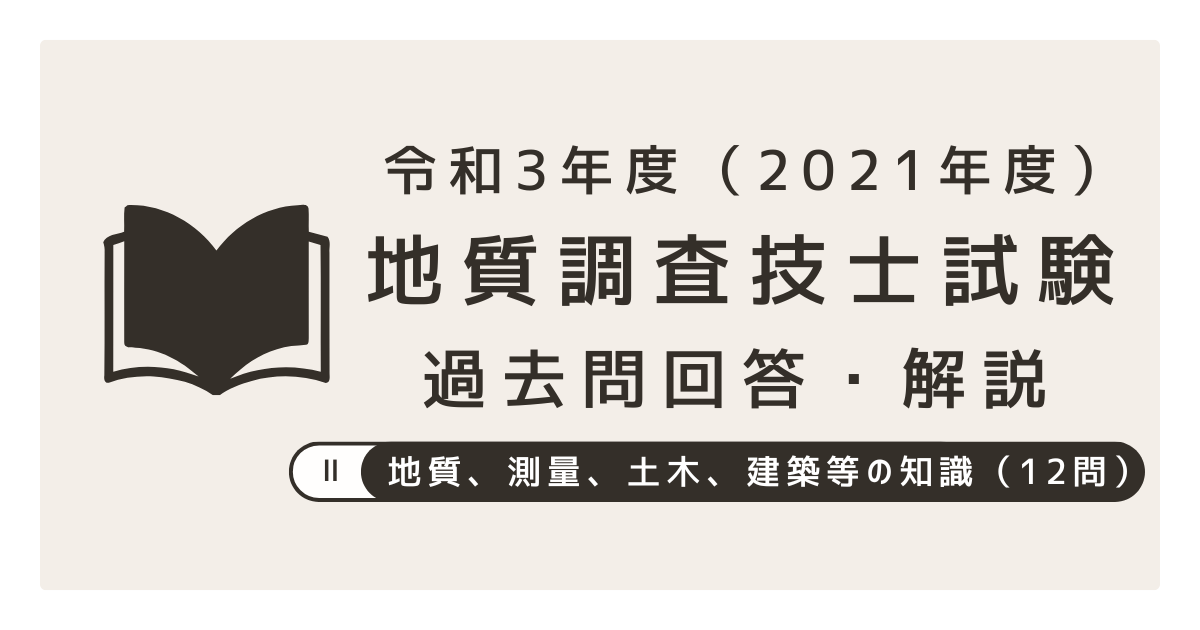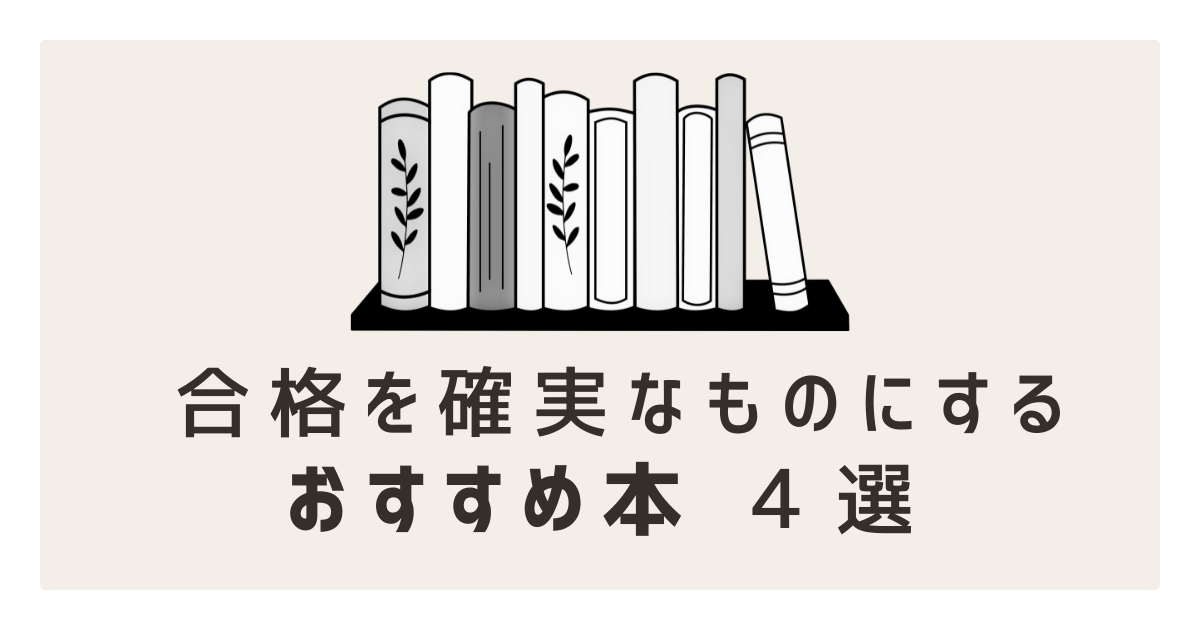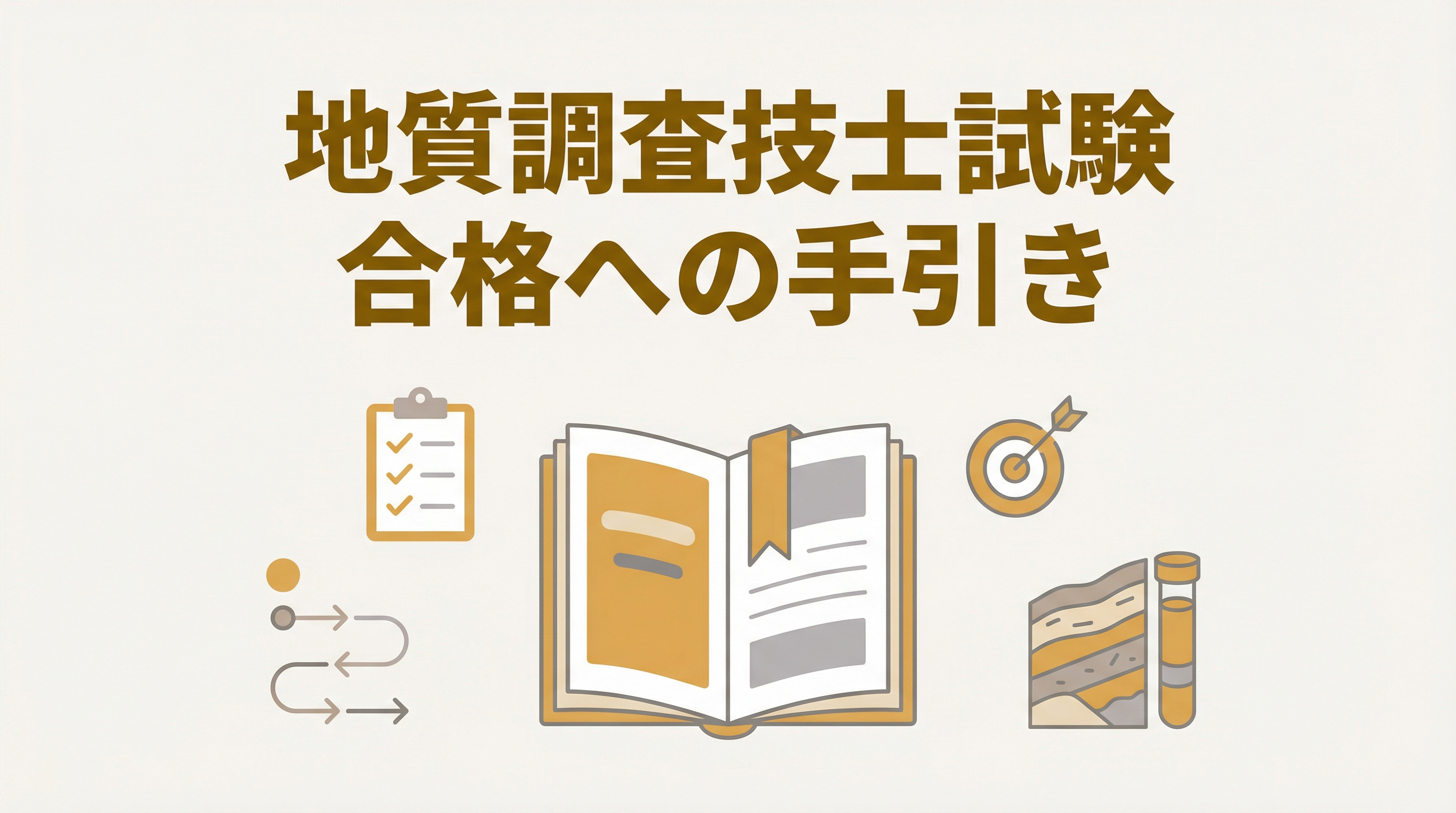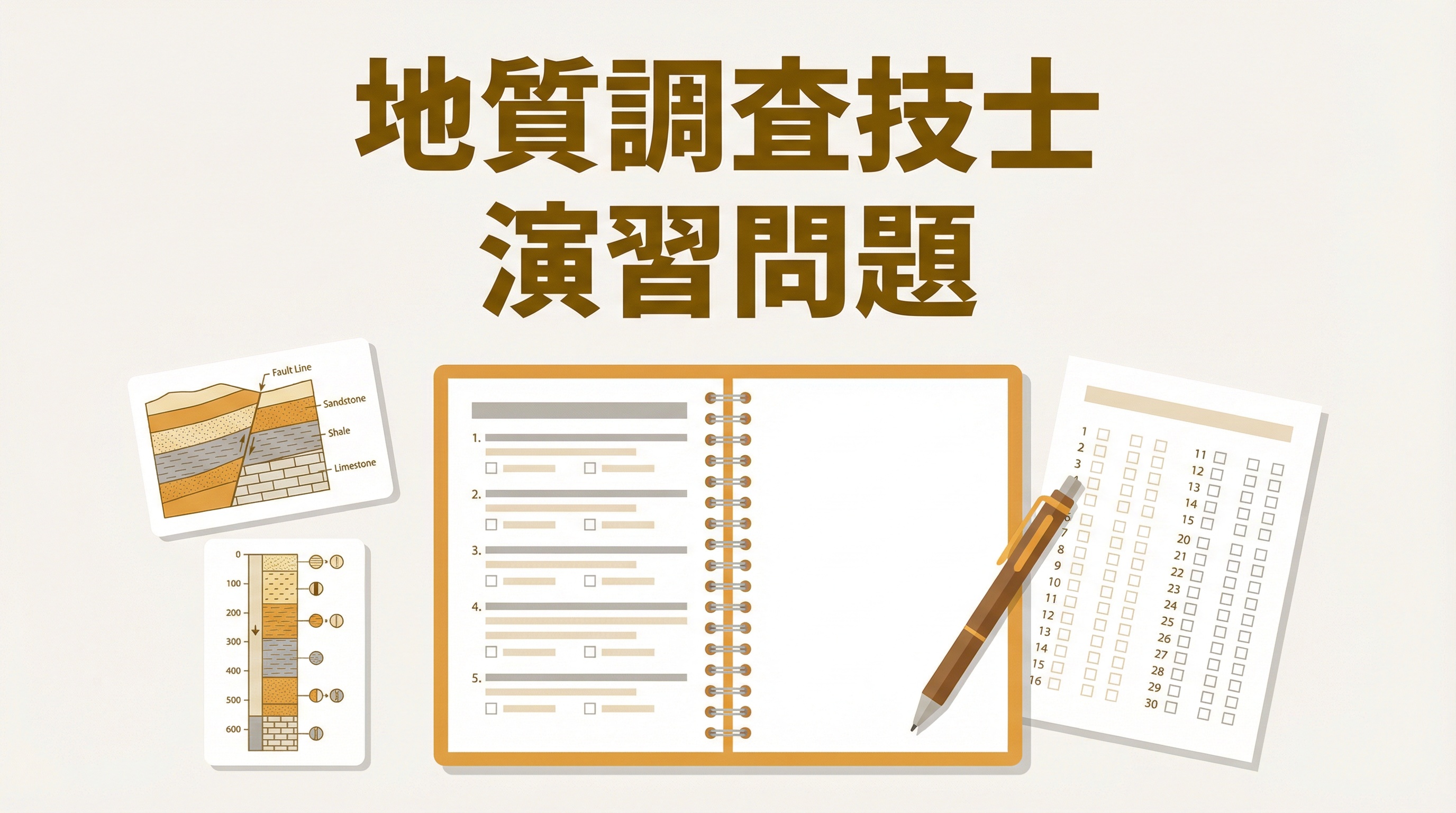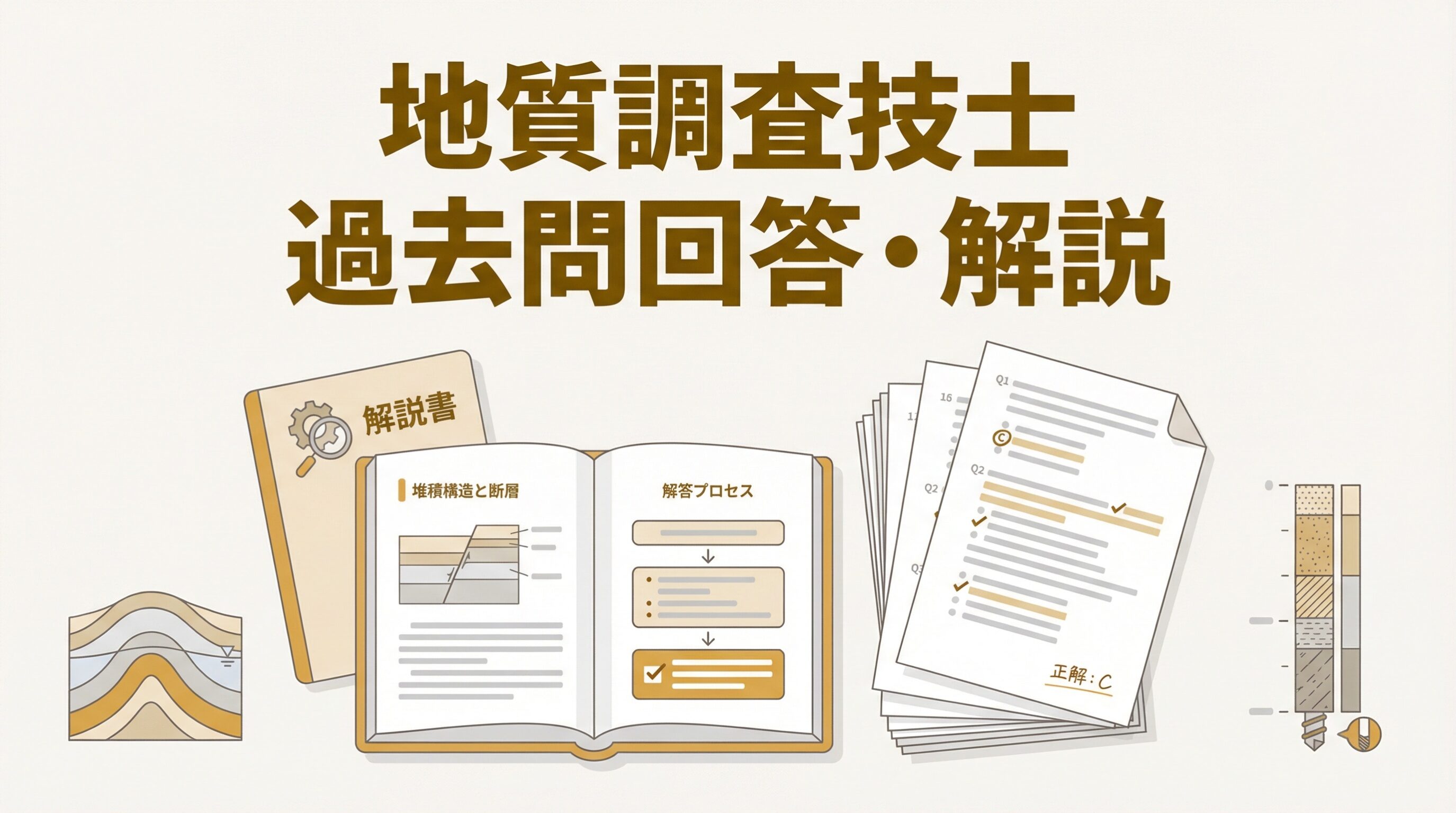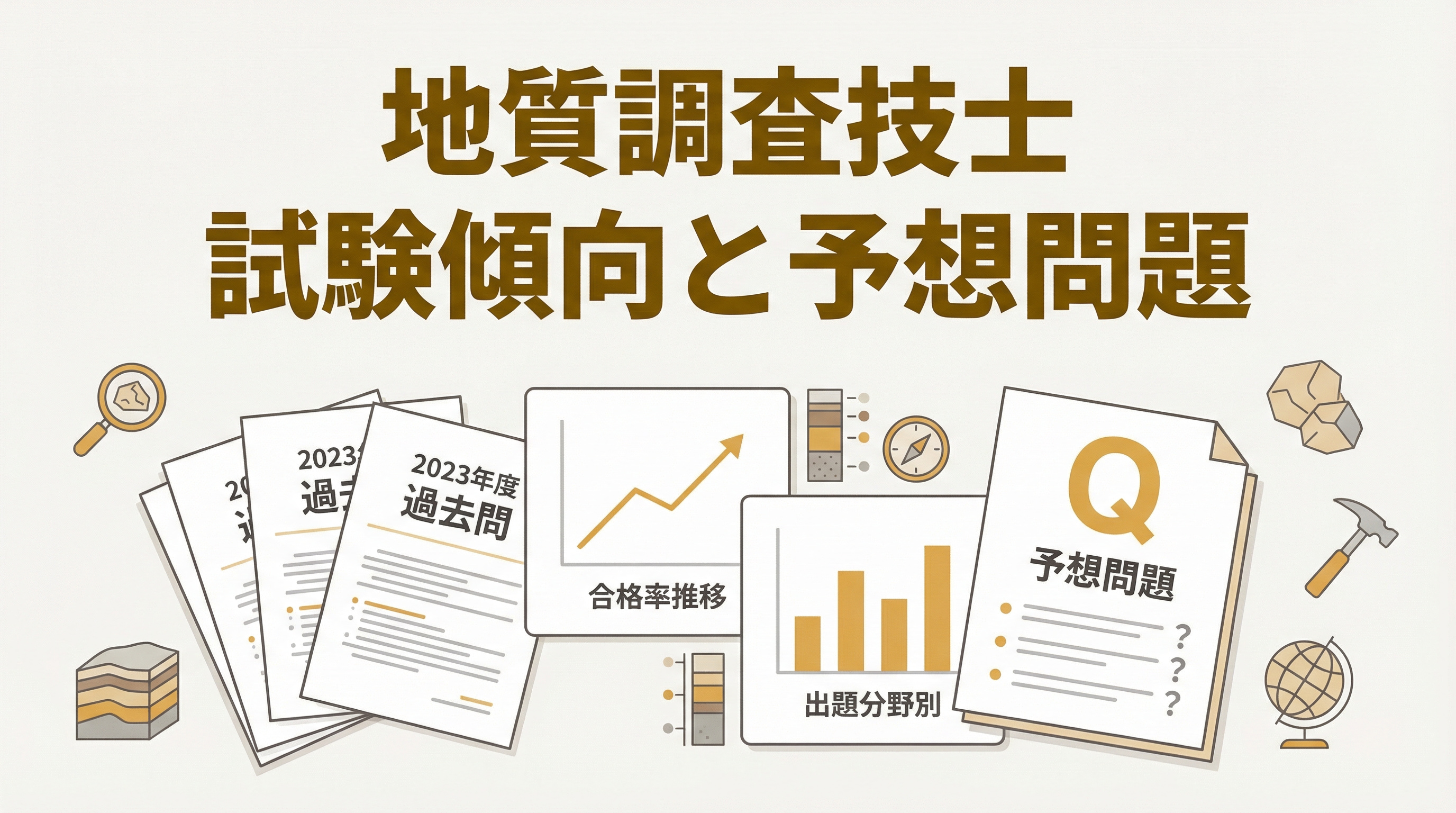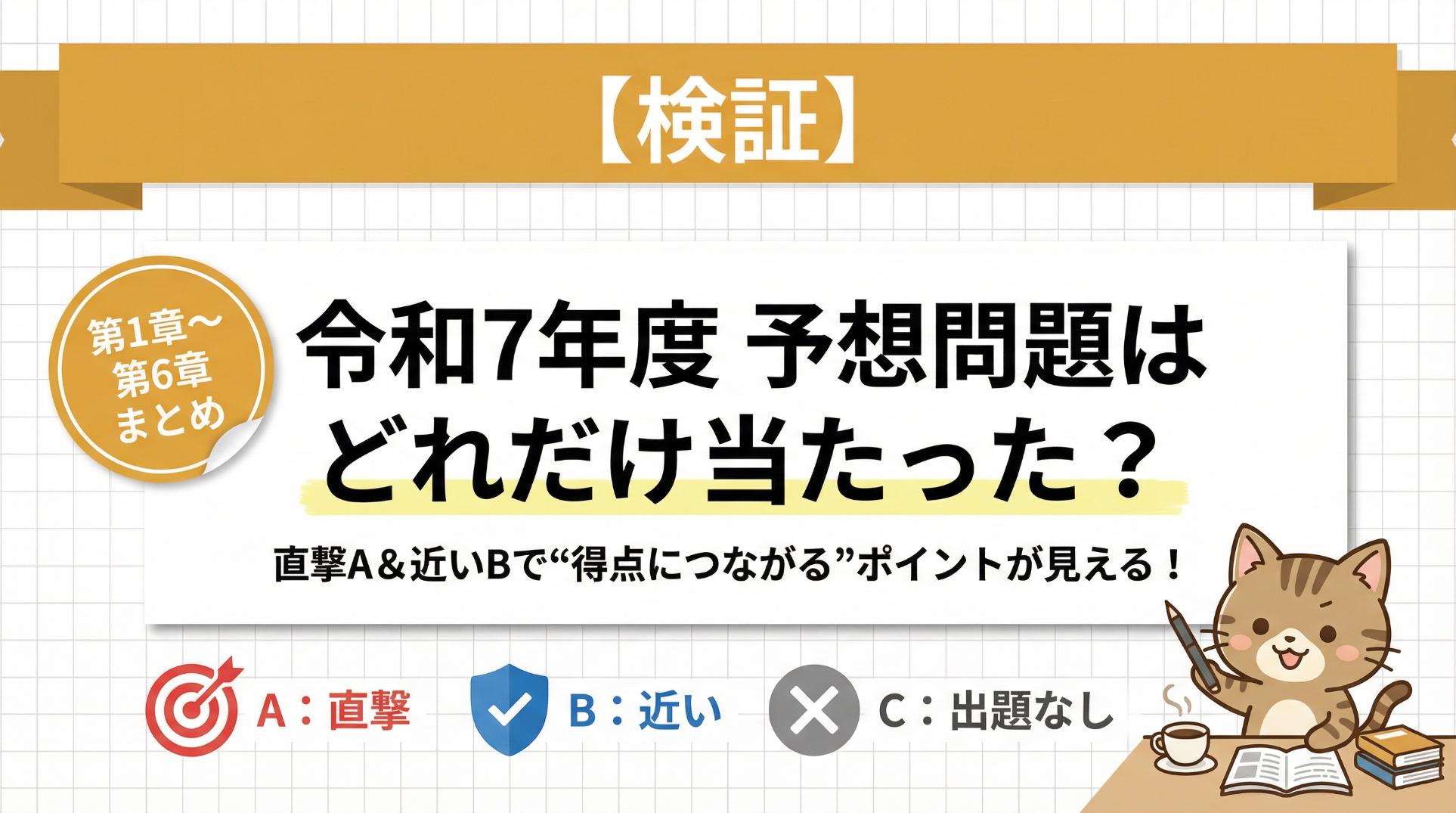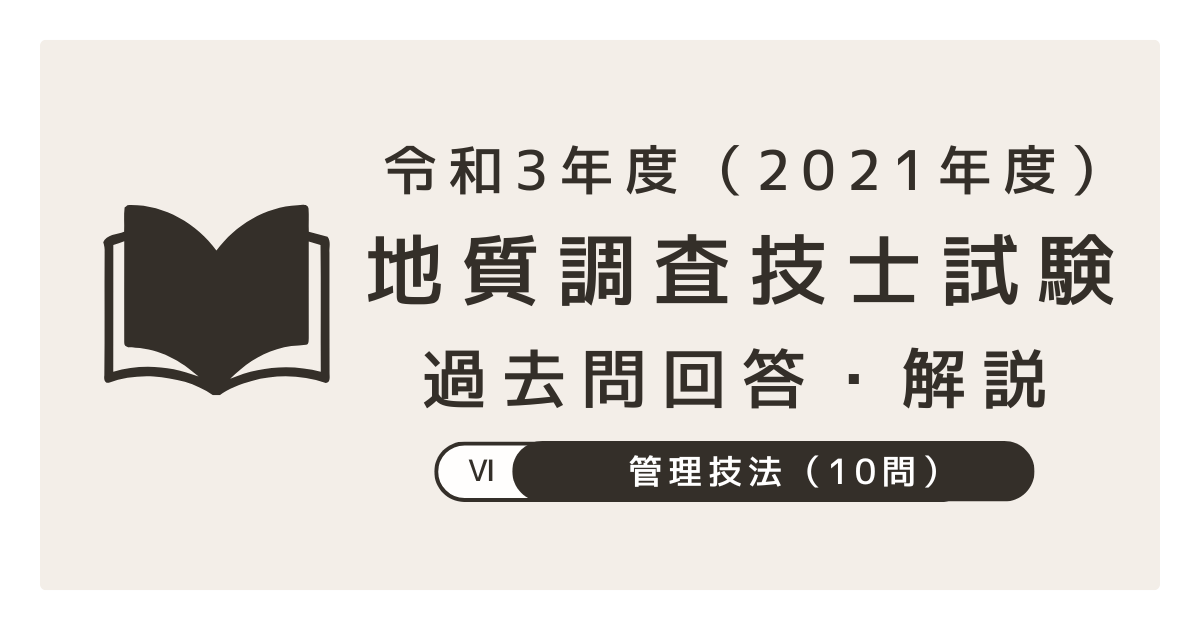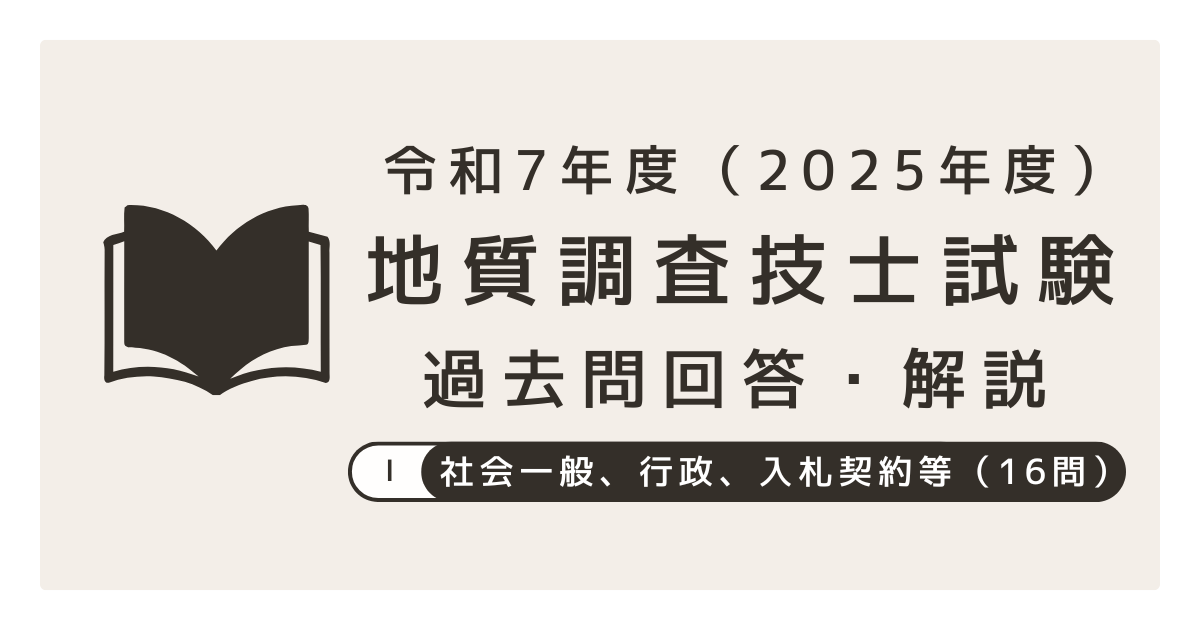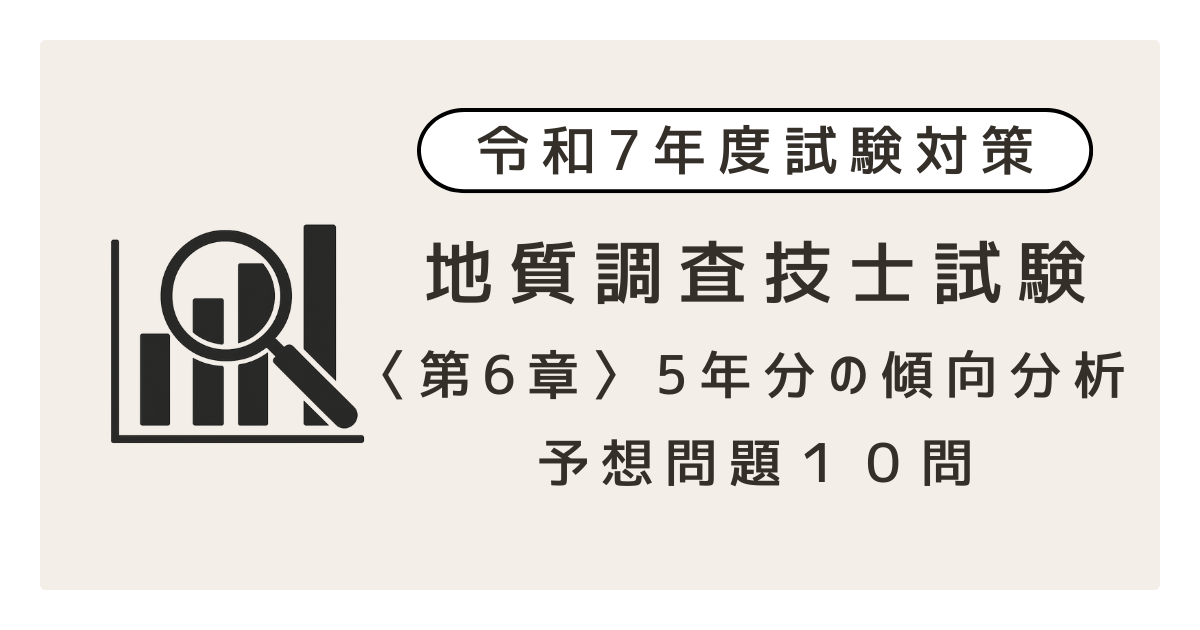【過去問回答&解説】令和3年度(2021年度) 地質調査技士資格検定試験(Ⅰ. 社会一般、行政、入札契約等(16問))
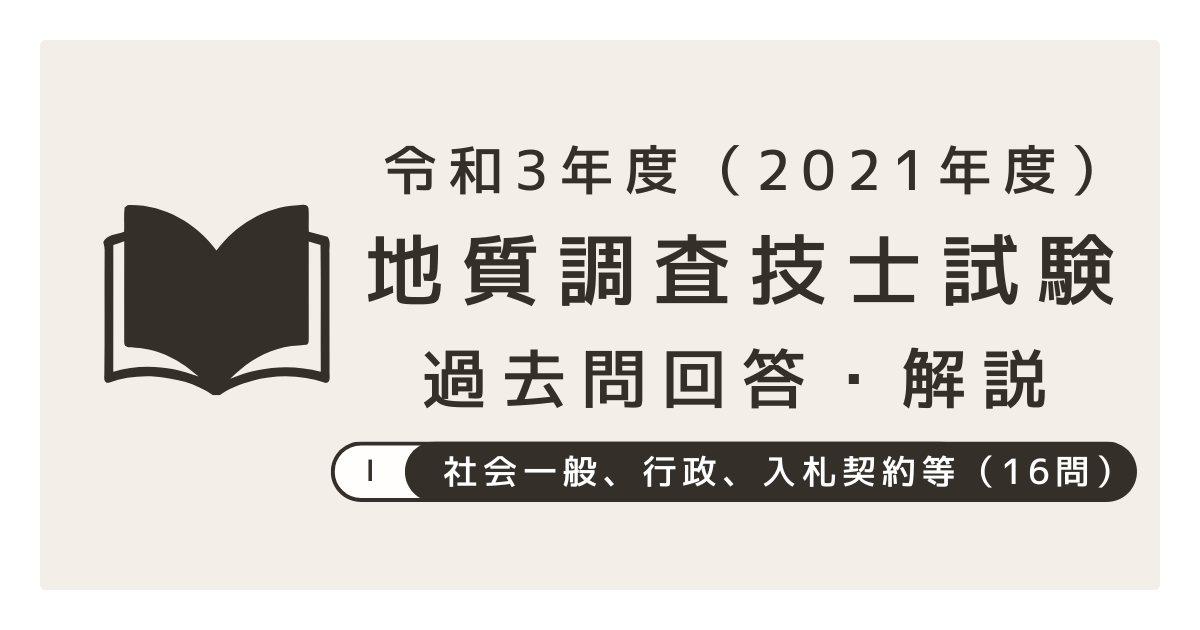
こんにちは!主任と申します
令和3年度 地質調査技士資格検定試験「現場技術・管理部門」(Ⅰ. 社会一般、行政、入札契約等(16問))の回答及び解説を作成しました
各問題の回答と解説は、「回答・解説はこちら→」に記載しています
地質調査技士の資格取得を目指す方々に少しでも役に立てば嬉しいです
令和3年度 地質調査技士試験「現場技術・管理部門」
Ⅰ. 社会一般、行政、入札契約等(16問)
問1. 次は,地質調査技士資格について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)地質調査業者登録規程の現場管理者の資格として認められている。
- (2)5年毎に登録更新の手続きが必要である。
- (3)地質調査業務発注の資格要件として多くの公的発注機関が活用している。
- (4)国土交通大臣認定資格である。
【回答・解説はこちら→】
正解は「4」。地質調査技士は民間(一般社団法人全国地質調査業協会連合会)が実施し、認定する資格検定制度であり、国(国土交通大臣)が認定する資格ではない(民間資格であり、国家資格ではない)。ちなみに、「現場調査部門」「現場技術・管理部門」「土壌・地下水汚染部門」の3部門は、平成27年に国土交通省技術者資格登録規定による登録を受けており、資格保有者については総合評価落札方式において加点評価対象となる。国土交通大臣認定資格と国土交通省登録資格は異なるため注意。
(参考サイト1 URL:https://www.zenchiren.or.jp/geo_comp/ 全地連HP「地質調査技士」)
(参考サイト2 URL:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html 国土交通省HP「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格について」)
問2. 次は,地質調査技士の行動指針を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)法令等の遵守
- (2)業界への説明責任
- (3)技術の向上
- (4)秘匿事項の保護
【回答・解説はこちら→】
正解は「2」。地質調査技士の行動指針は、一般社団法人全国地質調査業協会連合会が定めた倫理綱領に記されており、業界への説明責任は指針に含まれていない。倫理綱領については、記述試験の必須問題にも出題されるため、必ず覚えること。
(参考サイト URL:https://www.zenchiren.or.jp/jgca/jgca1_4.html 全地連HP「倫理綱領」)
問3. 次は,「河川法」における河川保全区域について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)河川管理者は,河川保全区域を指定するときは,国土交通省令で定めるところにより,その旨を公示しなければならない。
- (2)河川保全区域の指定は,当該河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
- (3)河川管理者は,河岸又は河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは,河川区域に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる。
- (4)河川管理者は,河川保全区域を指定しようとするときは,あらかじめ,国土交通大臣の意見をきかなければならない。
【回答・解説はこちら→】
正解は「4」。河川法において、河川管理者が河川保全区域を指定しようとするとき、国土交通大臣等に「意見を聞かなければならない」とは定めていない。河川管理者が指定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。ちなみに、国土交通大臣が河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない(変更や廃止しようとするときも同様)。
(参考サイト URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167#Mp-Ch_2-Se_4 e-GOV 河川法 第54条「河川保全区域」)
問4. 次は,令和 2 年 4 月から施行された公共土木設計業務等標準委託契約約款について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)制定以来約120年ぶりに債権関係の規定が改正された民法や国内外の契約状況を踏まえ,必要な改正が行われた。
- (2)受注者が有する登録意匠を設計等に用いる場合,意匠の実施を有償で承諾する。
- (3)契約不適合の責任期間は,原則として2年または3年となった。
- (4)「瑕疵」という用語が「契約不適合」に置き換えられた。
【回答・解説はこちら→】
正解は「2」。有償ではなく無償の間違い。
(参考文献:公共土木設計業務等標準委託契約約款 第8条の2「意匠の実施の承諾等」)
問5. 次は,「国土地盤情報データベース」について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)受注者は,仕様書等で定められた場合には,成果となる地盤情報を第三者機関による検定を受けた上で,「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない。
- (2)検定および登録の対象となる地盤情報は,「ボーリング柱状図」と「土質試験結果一覧表」である。
- (3)検定および登録に要する費用は,原則として受注者が負担することになっている。
- (4)一般財団法人国土地盤情報センターは,国土交通省から第三者機関として認定されており,検定料金はボーリング1本あたりの金額が定められている。
【回答・解説はこちら→】
正解は「3」。検定および登録に要する費用は、業務費用として積算に見込まれているため、受注者が負担するものではない。
(参考サイト URL:https://www.mlit.go.jp/tec/gyoumu_sekisan.html 国交省HP「設計業務等標準積算基準書および同(参考資料)」)
(参考文献:令和7年度 地質調査積算基準)
問6. 次は,第五次環境基本計画における分野横断的な重点戦略を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)国土のストックとしての価値の向上
- (2)災害に強い安全な国土づくり,危機管理に備えた体制の推進
- (3)健康で心豊かな暮らしの実現
- (4)持続可能性を支える技術の開発・普及
【回答・解説はこちら→】
正解は「2」。重点戦略は以下の6つ。
- 1.持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築
- 2.国土のストックとしての価値の向上
- 3.地域資源を活用した持続可能な地域づくり
- 4.健康で心豊かな暮らしの実現
- 5.持続可能性を支える技術の開発・普及
- 6.国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と戦略的パートナーシップの構築
(参考サイト URL:https://www.env.go.jp/press/105414.html 環境省HP「第五次環境基本計画の閣議決定について」)
問7. 次は,廃棄物処理について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)ベントナイト泥水は産業廃棄物である。
- (2)産業廃棄物処理業を営むためには,市町村長の許可が必要である。
- (3)排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合,産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付は不要である。
- (4)廃棄物処理法には罰則が定められており,国籍,性別,年齢を問わず国内にいるすべての人が対象となる。
【回答・解説はこちら→】
正解は「2」。市町村長ではなく、産業廃棄物処理業を行おうとする区域を管轄する「都道府県知事」の許可を受けなければならない。
(参考サイト URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137#Mp-Ch_3-Se_3 e-GOV 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条「産業廃棄物処理業」)
問8. 次は,ISO9001:2015(品質マネジメントシステム)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)業種および形態,規模,提供する製品を問わず,あらゆる組織に適用できる。
- (2)一貫した製品・サービスの提供と顧客満足度の向上を意図している。
- (3)業務上のリスク管理が含まれる。
- (4)この規格で要求される文書類は,この規格の箇条の構造と一致させる必要がある。
【回答・解説はこちら→】
正解は「4」。JIS Q9001(品質マネジメントシステム−要求事項)の「0.1 一般」に、この規格は「文書類をこの規格の箇条の構造と一致させる」ことを意図したものではないと記載がある。
(参考サイトURL:https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISNumberNameSearchList?toGnrJISStandardDetailList 日本産業標準調査会ウェブサイト「JIS Q9001」)
問9. 次は,大深度地下利用の大深度地下使用法について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)対象は,人口の集中度等を勘案して政令で定める地域である。
- (2)対象は,道路,河川,電気,ガス,上下水道等の公共の利益となる事業である。
- (3)土地所有者等は具体的な損失があっても補償を請求できない。
- (4)深さの基準は,地下40m以深または支持地盤上面から10m以深のうちいずれか深い方である。
【回答・解説はこちら→】
正解は「3」。損失があった場合、補償を請求できる。
(参考サイトURL:https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000012.html 国土交通省HP「大深度地下利用」)
問10. 次は,地質調査業者登録規定について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)地質調査業者の登録がなければ,地質調査業の営業を行うことができない。
- (2)地質調査業者登録を受けた者は,毎事業年度経過後4か月以内に,現況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- (3)地質調査業者登録の有効期間は5年間であり,継続する場合は満了の日の90日前から30日前までの間に更新申請が必要である。
- (4)地質調査業者登録の現場管理者と建設コンサルタント登録の技術管理者は,兼任することができない。
【回答・解説はこちら→】
正解は「1」。登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができる。
(参考サイトURL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000036.html 国土交通省HP「地質調査業者登録制度とは」)
問11. 次は,令和元年に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)測量,地質調査その他の調査及び設計が本法律の対象として位置付けられた。
- (2)情報通信技術を活用したテレワーク等による感染症対策の推進が規定された。
- (3)業務の実施時期の平準化のための債務負担行為・繰越明許費の活用が示された。
- (4)災害時の緊急対応の充実強化が図られた。
【回答・解説はこちら→】
正解は「2」。令和元年に改正されたポイントは以下の4つ。
- 1.災害時の緊急対応の充実強化
- 2.働き方改革への対応
- 3.生産性向上への取組
- 4.調査・設計の品質確保
「生産性向上への取組」の中で、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上が規定されているものの、「テレワーク等による感染症対策の推進」については規定されていない。ちなみに、令和6年6月に品確法は改定されている。
(参考サイトURL:https://www.mlit.go.jp/tec/reiwaunyoshishin.html 国土交通省HP「「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正について」)
問12. 次は,国土交通省におけるプロポーザル方式の対象となる地質調査業務を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)ボーリング調査
- (2)地質リスク調査検討
- (3)軟弱地盤調査・検討
- (4)トンネル変状調査・解析
【回答・解説はこちら→】
正解は「1」。ボーリング調査は「価格競争方式」「総合評価落札方式」の対象となる。
(参考文献:「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」(国土交通省))
問13. 次は,仕様書に関する事項について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)共通仕様書と特記仕様書において,同じ作業の指示内容が異なる場合は,共通仕様書を優先する。
- (2)共通仕様書は発注業務特有の事項を記載したものであり,特記仕様書は発注者毎に定められている業務に共通して適用されるものである。
- (3)共通仕様書と特記仕様書において,同じ作業の指示内容が異なる場合は,受注者は発注者に確認しなければならない。
- (4)共通仕様書および数量総括表に記載された事項は特記仕様書に優先する。
【回答・解説はこちら→】
正解は「3」。(1)同じ作業の指示内容が異なる場合は、受注者は発注者に確認しなければならない。(2)各仕様書の説明が逆になっている。「共通仕様書」は各業務に共通する技術上の指示事項等を定めた図書。「特記仕様書」は共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細又は特別な事項を定めた図書。(4)設計図書(仕様書や数量総括表等)は相互に補完し合うものであるため、いずれかの仕様書等を優先するのは間違い。
(参考文献:国土交通省「土木設計業務等共通仕様書(案)」)
問14. 次は,TECRIS(テクリス)について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)TECRIS システムへの登録は,発注機関の仕様書等により登録を義務付ける旨の定めがある業務のみ可能であり,受注者による任意登録は認められていない。
- (2)登録は,原則として業務受注時,業務内容変更時(請負金額変更などが行われた時),および業務完了時に行う。
- (3)登録に際しては,発注機関担当者が内容を確認して署名した「登録のための確認のお願い」を JACIC に提出しなければならない。
- (4)業務完了時の登録では,業務実績データとして業務キーワードを最大 10 個登録することができる。
【回答・解説はこちら→】
正解は「1」。テクリスへの登録の対象となる業務には、「登録義務業務」と「任意登録業務」があるため、受注者による任意登録も認められている。
(参考サイトURL:https://cthp.jacic.or.jp/tecris/record/guide/check/ コリンズ・テクリス「登録対象業務と登録時期」)
問15. 次は,公共土木設計業務等標準委託契約約款における契約不適合責任について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)発注者は,成果物が品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは,受注者に履行の追完を請求できる。
- (2)発注者は,受注者がこの契約の成果物を完成させることが出来ないことが明らかなときは,直ちにこの契約を解除する事ができる。
- (3)発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等はできない。
- (4)発注者の指示により生じた成果物の契約不適合の場合であっても,受注者に当該契約不適合に関する請求等をする事ができる。
【回答・解説はこちら→】
正解は「4」。発注者の指示により生じた成果物の契約不適合の場合、発注者は当該契約不適合を理由に請求等をすることができない。ただし、受注者がその指示を不適当であると知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(参考文献:公共土木設計業務等標準委託契約約款 第53条「契約不適合責任期間等」)
問16. 次は,公共土木設計業務等標準委託契約約款について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
- (1)受注者は,成果物が著作物に該当する場合において,発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変する場合には改変に同意する。
- (2)受注者は,業務の全部を一括して,または発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,または請負させることはできない。
- (3)受注者は,地元関係者との交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
- (4)受注者が,調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得る。
【回答・解説はこちら→】
正解は「3」。受注者ではなく、発注者が費用を負担しなければならない。
(参考文献:公共土木設計業務等標準委託契約約款 第12条「地元関係者との交渉等」)
解説については図書や他サイトを参考に記述していますが、
私自身、勉強している身であるため、言葉足らずな点や間違い等あるかと思います
もし、間違い等あった場合は記事にコメントを残していただけると幸いです